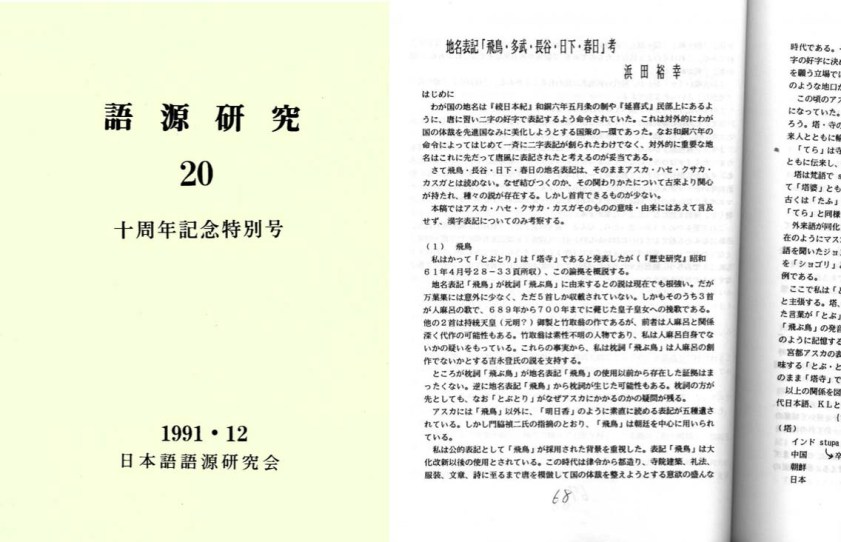(3)論文
地名表記「飛鳥・多武・長谷・日下・春日」考 浜田 裕幸
『語源研究』第20号 平成3年12月8日 68-73頁 所収(1991年)
はじめに
わが国の地名は『続日本紀』和銅六年五月条の制や『延喜式』民部上にあるように、唐に習い二字の好字で表記するよう命令されていた。
これは対外的にわが国の体裁を先進国なみに美化しようとする国策の一環であった。
なお和銅六年の命令によってはじめて一斉に二字表記が創られたわけでなく、対外的に重要な地名はこれに先だって唐風に表記されたと考えるのが妥当である。
さて飛鳥・長谷・日下・春日の地名表記は、そのままアスカ・ハセ・クサカ・カスガとは読めない。
なぜ結びつくのか、その関わりかたについて古來より関心が持たれ、種々の説が存在する。しかし首肯できるものが少ない。
本稿ではアスカ・ハセ・クサカ・カスガそのものの意味・由来にはあえて言及せず、漢字表記についてのみ考察する。
(1) 飛鳥
私はかって「とぶとり」は「塔寺」であると発表したが(『歴史研究』昭和61年4月号28-33頁所収)、この論拠を概説する。
地名表記「飛鳥」が枕詞「飛ぶ鳥」に由来するとの説は現在でも根強い。
だが万葉集には意外に少なく、ただ5首しか収載されていない。
しかもそのうち3首が人麻呂の歌で、689年から700年までに薨じた皇子皇女への挽歌である。
他の2首は持統天皇(元明?)御製と竹取翁の作であるが、前者は人麻呂と関係深く代作の可能性もある。
竹取翁は素性不明の人物であり、私は人麻呂自身でないかの疑いをもっている。
これらの事実から、私は枕詞「飛ぶ鳥」は人麻呂の創作でないかとする吉永登氏の説を支持する。
ところが枕詞「飛ぶ鳥」が地名表記「飛鳥」の使用以前から存在した証拠はまったくない。
逆に地名表記「飛鳥」から枕詞が生じた可能性もある。
枕詞の方が先としても、なお「とぶとり」がなぜ「アスカにかかるのかの疑問が残る。
アスカには「飛鳥」以外に、「明日香」のように素直に読める表記が五種遺されている。
しかし門脇禎二氏の指摘のとおり、「飛鳥」は朝廷を中心に用いられている。
私は公的表記として「飛鳥」が採用された背景を重視した。
表記「飛鳥」は大化改新以後の使用とされている。
この時代は律令から都造り、寺院建築、礼法、服装、文章、詩に至るまで唐を模倣して国の体裁を整えようとする意欲の盛んな時代である。
そのような背景で、宮都アスカの表記を対外的に恥ずかしくない二字の好字に決めることは、飛鳥朝にとって焦眉の急だったはずである。
国威発揚を願う立場では、「鳥は朝、ねぐらから出て、まず飛び渡るから、朝→アスカ」のような地口から「飛鳥」を採用したとは考え難い。
この頃のアスカは数多くの寺の大屋根と塔がそびえる極めてエキゾチックな都になっていた。
塔・寺は宮都アスカのシンボルであり、アスカ人の誇りであったろう。
塔・寺の建築は朝鮮からの技術者に負うが、「たふ」「てら」はこれら渡来人とともに輸入された借用語と考えるのが妥当である。
「てら」は寺の字音でなく、礼拝所を原義とする古代朝鮮語の tj§l が仏教とともに伝来し、転訛して固定したものと考えられている。
塔は梵語で stupa といい、古代中国では音訳して「卒塔婆」「率都婆」、略して「塔婆」とも「塔」ともいう。
日本では現在「とう to 」と発音されているが、古くは「たふ」である。
「たふ」は塔の字音ではあるが、直接中国からでなく「てら」と同様古代朝鮮経由の外来語であろう。
外来語が同化されて固定するまでの過渡期ではいろいろの発音が存在する。現在のようにマスコミの発達した時代とは事情が違う。予備知識を持たずに直接英語を聞いたジョン万次郎は「日曜」を「ションレイ」、小泉八雲夫人は「砂糖」を「ショゴリ」と記している。
トロッコとトラック、メリケンとアメリカンも同例である。
ここで私は「とぶとり」の「とぶ」とは塔のことであり、「とり」は寺であると主張する。
塔、寺が「たふ」「てら」に固定するまでに、渡来人から直接聞いた言葉が「とぶ」「とり」と受け取られた場合があったと推論する。
まして倭語「飛ぶ鳥」の発音との近似性にひかれて、「塔寺」から「飛ぶ鳥」を連想し、そのように記憶することは充分考えられる。
bucket と馬穴の関係と同様である。
宮都アスカの表記の決定に腐心していた飛鳥朝が、アスカを象徴する塔寺を意味する「とぶ・とり」の類音「飛鳥」を採用したとするのが私の結論である。
そのまま「塔寺」では国際的に不適当であろう。
以上の関係を図示しておく。
ここで、KPとJPは塔にあたる古代朝鮮語と古代日本語、KLとJLは寺にあたる古代朝鮮語と古代日本語を意味する。
{古代} {現代}
(塔)
インド stupa
中国 卒塔婆・塔婆
朝鮮 KP ------------------------------------→ tap
日本 JP (tobu,tabu,tamu,taFu) -→ taFu --→ to
{古代} {現代}
(寺)
朝鮮 KL -------→ tj§l --------------------→ t,§l
日本 JL (toli,tela) -----------→ tela -→ tela
stupa≧KP≧JP --① KP≧tap --② JP ≧taFu --③
以上の3つの不等式を解くと KP≒tap
また KP≧JP であるから
故に JP≒tobu,tamu はありうる。
同様にして JL≒toli もありうる。
枕詞「飛ぶ鳥(の)」が地名表記「飛鳥」以前に存在していたと仮定しても、「塔寺(の)」は土地ほめの働きがあり、アスカの冠辞としてふさわしいものである。
逆に表記「飛鳥」から枕詞が生じたとして、人麻呂が公的な挽歌に枕詞「飛ぶ鳥」を使用したことは、あるいは新しい表記「飛鳥」の広報活動を担っていたのかもしれない。
人麻呂には刑死説がある。
これに基づいて、私はさらに speculative な考えを持っている。
万葉集に明日香を詠んだ歌は多いのに、冠辞「とぶとりの」があまり使用されていないのはなぜか。
私はこの枕詞が人麻呂が作ったものである故に、人麻呂失脚後からしばらくの間、使用することがタブーになっていたのでないかと想像している。
(2)多武峰・談山
飛鳥の東、談山神社の鎮座する山は現在「多武峰」と表記され、地元では「tonomine」と発音されている。
このあたりは、古くは倉梯・椋橋(くらはし)と呼ばれたが(崇峻即位前紀8月条・崇峻5年11月条・天武7年条・万290)、斎明紀2年条に「田身嶺(大務)」、持統紀7年9月条に「多武嶺」がみられ、談山神社参道の古い石の道標には「たふのミ祢」と遺されている。
一方談山については、『多武峯縁起』に「中大兄皇子中臣鎌足連に言って曰く、鞍作の暴虐之をいかにせん。願くは奇策を陳べよと。中臣連皇子を将いて城東の倉橋山の峯に登り藤の花の下に撥乱反正の謀を談ず--中略--仍て其の談処を号して談岑と曰う」の記述がある。
しかし私はこの話は牽強附会と思う。多武峰=タム>タン>談山、つまりまず多武峰があってこれを転じて談山としたのが第一義であると考える。
藤原鎌足の話は第二義的であるか、あるいは後世の創作であろう。
さらに私は「多武峰」は「塔の峰」と考える。
既に下河辺長流は『万葉集管見』で「多武の山は和州塔の峯なり」と記述している。
藤原鎌足は天智8年(669)に死亡した。
当時唐で修業していた長子の定慧和尚は帰朝後、弟不比等と相談の上、父の供養のため多武峯に十三重塔婆を建てたと伝えられる。
飛鳥時代の人にとって、山上に塔が建ったことは非常に印象的であったにちがいない。
そこで人々がこの山を「塔の峰(山)」と呼んだ可能性は非常に大きく、またこれは素朴で自然な命名である。
「ふさ手折り多武の山霧(万1704)」のように、多武が(たわむ)からきたとする説があるが、なぜこの山だけがたわむかの疑問を説明しにくい。
それでは、塔(たふ)がなぜ「たむ」かは前章の図で明らかであろう。
また、阿麻登夫(天飛ぶ・記歌謡85)の転訛である阿麻陀牟(記歌謡83)も参考になる。
逆に、「飛鳥」の「とぶ」が塔であるとする私の説の補強になる。
(3)長谷
大和の長谷寺がある地は現在ハセと発音されているが、古代はハツセ(雄略紀6年歌謡77に播都制、継体紀7年歌謡97に簸細)といわれた。
表記としては泊瀬(雄略即位前紀、万79)、初瀬、長谷(雄略記、万425)などがある。
問題の長谷は飛鳥と同様そのままハツセとは読めない表記である。
その関わり方については、本居宣長が『古事記伝』四十一之巻に「長谷と書ことは地のさまに因てなるべし」と記しているように、現地を訪ねてみれば誰でも理解できる。
長谷は初瀬川の長い谷間にあるからである。
しかし私が問題にしているのは、初瀬のような簡単な2字の好字があるのに、何故わざわざ「長谷」という表記があり、またよく使われたのかということである。
「長谷(ナガタニ)の初瀬」という枕詞からきたとする説があるが、「コモリク(隠国・隠口)の初瀬」はあっても、「ナガタニの初瀬」の古例は遺されていない。つまり証拠がない。
仮にこの枕詞が存在したとしても、地名表記に長谷を採用した理由が理解しにくい。
長谷の地は古くは雄略天皇が即位した所で、天武天皇の皇女の大來皇女が伊勢の斎王に立つ前年に泊瀬の斎宮に入っている。
天武天皇は泊瀬に行幸し酒宴を開いた。持統天皇も後に行幸している。
長谷寺法華説相図銅板の銘文や『長谷寺縁起』によると、天武天皇の病気平癒を祈願して法華説相図が奉納されている。
このように隠国の長谷は聖地であるだけでなく、酒宴を催す行楽地の性格も持っていたようである。
「長い谷」というのは素朴な表記で、自然環境を端的に表現する地形語地名である。
地名の発生段階から考えると、山口恵一郎氏によれば素朴命名段階(期)に多い地名である。
例えばニューヨーク市の Long Island と同列の命名であるが、「長谷」は(ハツセ)と読めないので庶民には無縁の表記である。
太平洋戦争後、日本を占領した米軍は代々木練兵場に宿舎を建てワシントン・ハイツと呼び、主要道路にはテキサス・ストリートのような標識を立て占領軍人にわかりやすくした。私は「長谷」にこれを連想する。
日本は白村江の戦いで唐・新羅連合軍に大敗した。その後郭務・劉徳高・金高訓のような唐・新羅の要人が次々と来日している。
朝廷は当然彼らを饗応しているが、宮都飛鳥に近い泊瀬に迎賓館のような接待用の建物が存在していたのでないかと私は想像している。
そして彼らに「ハツセ」という所がすぐ理解できる地形語地名「長谷」を採用したのでないかと推理している。
つまり「長谷」の表記は地元の人のためでなく、外来者用に作られたと考える。
さらに表記「長谷」は天武または持統朝から使用されたのでないかと推論している。
(4)日下
神武東征軍がはじめ浪速に上陸した所を記紀は草香・日下と記している。
古事記序文で太安万侶が「姓に於きて日下を玖沙訶と謂ひ、云々」と述べているように、当時すでに地名表記「日下」とクサカの関わりかたが不明になっていたことがわかる。
この関係について、古くから賀茂真淵、本居宣長などの諸説があるものの最近まで納得できる説がなかった。
谷川健一氏は『白鳥伝説』(1986年刊)で「日下」は「ヒノモト」であると喝破された。
そして邪馬台国の東遷以前に、河内・大和に移住していた物部と先住民蝦夷の連合国ヒノモトについて壮大な説を展開されている。
河内と大和の国境に生駒山地が横たわっているが、その北端近くの河内側の麓あたりが日下の地とみられている。
現在も日下町の名が残り、近くに饒速日命を祭る石切剣箭神社がある。
古代の大阪は現在大阪城のある上町台地が半島状に南から突き出し、その東側には河内湖が生駒山麓までひろがっていた。
大阪城の南に隣接して難波宮趾があるが、この上町台地には何層にも古代遺跡が確認されている。
この地は水産資源に恵まれ、また水上交通の拠点であるため居住に適し、縄文時代中期以来、数千年におよぶ定住集落があったと考えられている。
谷川氏は難波から真東に日下が位置している事実に注目し、種々の角度からの考察を加えて次のように結論されている。
日下は難波からみて太陽の昇るところから「ヒノモトのクサカ」が生じた。日下は太陽信仰の原点であり、太陽祭祀の中心であった。
以上が日下に関する谷川説であり、私は全面的に賛成するものである。
ただ、難波と日下の関係は太陽信仰から発したにせよ、後に春分・秋分の観測に重要な意味をもつようにになったと私は考える。
これについては次章で述べる。
(5)春日
春日は現在の奈良市の東部丘陵地帯にあたる。
武烈天皇即位前紀に「播比箇須我(歌謡94)」、継体天皇紀7年に「播比能須我能倶(歌謡96)」が遺されている。
そこでカスガにかかる枕詞の「春日(はるひ)」が地名表記に借用されたものと理解されている。
それでは、なぜ春日(はるひ)がカスガにかかるのか。
春の日はよく霞がかかる、このカスムとカスガが類音であることを介して連結したとの説が有力である。
しかし私はこの説に少し抵抗を感じる。直接連結するのでなく霞を介さねばならないからである。
世界中どこの古代社会でも農耕などの共同作業をする上に、季節の周期を正確に予測する必要があった。
なかでも日の出、日没で見分けられる春分・夏至・秋分・冬至の四つの日が、季節を決めるのに最も重要なものとなっていた。
英国のストンヘンジ、米国のメデスン・ホイールの柱群遺跡はその観測のための施設だったと考えられている。
なお日本書紀には天武4年正月に「始興占星台」の記述がある。
春分の日に太陽は真東から昇り真西に没む。古代人にとっては、暖かさと生命の復帰を示す日であった。
この日にはまた、夜と昼の時間がほぼ同じ長さになり、農業社会では土地に種まきの準備をすべき日として知られていた。
春分は復活と再生の時であった。キリスト教の復活祭がほぼ同じ頃であるのは、偶然の一致ではない。
古代の日本でも事情は同じはずである。
例えば春分の日を観測するためには、ある地点から見て眞東(西)に太陽が昇る(沈む)日を観測すればよい。
ストンヘンジのように柱をたてずとも、山のような自然の目印を利用すればたりる。
私は難波宮から真東に日下があり、さらにその延長上に春日山があることに注目した。
私は日下、春日山が春分の日の決定のための観測に用いられたと考える。
そしてこのことが「春日(はるひ)のカスガ」の枕詞を生み出し、また春日がカスガの地名表記となった第一義の理由であると推論する。
私は春日の表記を考えているうちに、上町台地-日下-春日の東西線に着目したが、以前箸墓-長谷-伊勢を結ぶ東西線の意味を発表された小川光三氏も難波宮-御蓋山を結ぶ「謎のライン(太陽の道)」を考えられている。
氏は太陽信仰を重視されている点、私と立場を異にする。 (1991.9.23)