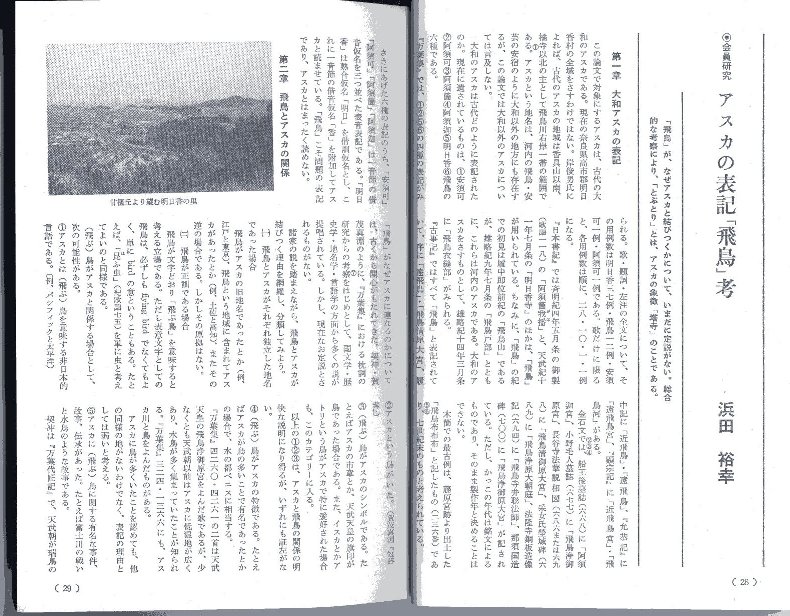
【 付編 】 過去に発表した拙論や、関係する諸件を掲載する。
(1)論文 アスカの表記「飛鳥」考 浜田 裕幸
『歴史研究』昭和61年4月号28-33ページ所収、新人物往来社 (1986年)
「飛鳥」が、なぜアスカと結びつくかについて、いまだに定説がない。
総合的な考察により、「とぶとり」とは、アスカの象徴「塔寺」のことである。
第一章 大和アスカの表記
この論文で対象にするアスカは、古代の大和のアスカである。現在の奈良県高市郡明日香村の全域をさすわけではない。
岸俊男氏によれば、古代のアスカの地域は香具山以南、橘寺以北の主として飛鳥川右岸一帯の範囲である。①
アスカという地名は、河内の飛鳥・安芸の安宿のように大和以外の地方にも存在するが、この論文では大和以外のアスカについては言及しない。
大和のアスカは古代どのように表記されたのか。
現在に遺されているものは、①安須可②阿須可③阿須箇④阿須迦⑤明日香⑥飛鳥の6種である。
『万葉集』では、①②⑤⑥の4種の表記がみられる。歌・題詞・左注の全文について、
その用例数は明日香37例・飛鳥12例・安須可1例・阿須可1例である。
歌だけに限ると、各用例数は順に、28・10・1・1例になる。
『日本書紀』では斉明紀四年五月条の御製(歌謡118)の「阿須箇我播」と、天武紀十一年七月条の「明日香寺」のほかは、「飛鳥」が用いられている。
ちなみに、「飛鳥」の紀での初見は履中即位前紀の「飛鳥山」であるが、雄略紀九年七月条の「飛鳥戸郡」とともに、これらは河内のアスカである。
大和のアスカをさすものとして、雄略紀十四年三月条に「飛鳥衣縫部」がみられる。
『古事記』ではすべて「飛鳥」と表記されていて、序に「遠飛鳥」・「飛鳥清原大宮」、履中記に「近飛鳥」・「遠飛鳥」、『允恭記』に「遠飛鳥宮」、『顕宗記』に「近飛鳥宮」・「飛鳥河」がある。
金石文②③④では、船王後墓誌(668年)に「阿須迦宮」、小野毛人墓誌(677年)に「飛鳥浄御原宮」、長谷寺法華説相図(686または698年)に「飛鳥清御原大宮」、采女氏塋域碑(689年)に「飛鳥浄原大朝庭」、法隆寺銅板造像記(694年)に「飛鳥寺弁聡法師」、那須国造碑(700年)に「飛鳥浄御原大宮」が記されている。
ただし、かっこの年代は銘文によるものであり、そのまま製作年と決めることはできない。
木簡での最古例は、藤原宮跡より出土した「飛鳥布布布」と記したもの(236番)であり⑤⑥、七世紀末のものと考えられている。
さきにあげた6種の表記のうち、「安須可」「阿須可」「阿須箇」「阿須迦」は一音節の借音仮名を三つ並べた表音表記である。
「明日香」は熟合仮名「明日」を借訓仮名とし、これに一音節の借音仮名「香」を附加してアスカと読ませている。
「飛鳥」こそ問題の表記であり、アスカとはまったく読めない。
第二章 飛鳥とアスカの関係
「飛鳥」がなぜアスカに連なるのかについては、古くから関心がもたれてきた。
契沖・賀茂真淵のように、『万葉集』における枕詞の研究からの考察⑦をはじめとして、国文学・歴史学・地名学・言語学の方面から多くの説が提唱されている。
しかし、現在なお定説とされるものがない。
諸家の説を踏まえながら、飛鳥とアスカが結びつく理由を網羅し、分類してみよう。
(一)飛鳥とアスカがそれぞれ独立した地名であった場合
飛鳥がアスカの旧地名であつたとか(例、江戸と東京)、飛鳥という地域に含まれてアスカがあつたとか(例、土佐と高知)、またその逆の場合である。しかしその原拠はない。
(二)飛鳥が正訓である場合
飛鳥が文字どおり「飛ぶ鳥」を意味すると考える立場である。
ただし表意文字としての飛鳥は、必ずしもflying bird でなくてもよく、単にbirdの意ということもある。たとえば、「昆ふ虫」(紀歌謡75)を単に虫と考えてよいのと同様である。
(飛ぶ)鳥がアスカと関係する場合として、次の可能性がある。
①アスカとは(飛ぶ)鳥を意味する非日本的言語である。(例、パシフィックと太平洋)
②アスカという鳥がいた。(賀茂其淵『冠辞考』)
③(飛ぶ)鳥がアスカのシンボルである。
たとえばアスカの市章とか、天武天皇の旗印が鳥であつた場合である。また、イスカとかアトリという鳥がアスカで特に愛好された場合も、このカテゴリーに入る。
以上の①②③は、アスカと飛鳥の関係の明快な説明になり得るが、いずれにも証左がない。
④(飛ぶ)鳥がアスカの特徴である。
たとえばアスカが鳥の多いことで有名であつたとかの場合で、水の都ベニスに相当する。『万葉集』4260・4261の二首は天武天皇の飛鳥浄御原宮をよんだ歌であるが、少なくとも天武朝以前はアスカに低湿地が広くあり、水鳥が多く集まっていたことが知られる。『万葉集』324・1366にも、アスカ川と鳥をよんだものがある。
アスカに鳥が多くいたことを認めても、他に同様の地がないわけでなく、表記の理由としては弱いと考える。
⑤アスカに(飛ぶ)鳥に関する有名な事件、故事、伝承があった。
たとえば富士川の戦いと水鳥のような故事である。
葵沖は『万葉代匠記』で、天武朝が瑞鳥の出現により朱鳥と改元したことを記念として、飛鳥が用いられるようになったと説いた。
本居宣長も『古事記伝』三八で同様の主張をしている。
しかしこれに対しては、井手至氏⑧・土橋寛氏⑨・川副武胤氏⑩の反論があり、契沖説の弱点は明らかであろう。
⑥アスカの地形とか山などの形が鳥に似ている。
川副武胤氏⑩は、アスカは飛翔する鳥の構図を描いていたと論証している。
⑦アスカに(飛ぶ)鳥のイメージがあった。
古代人が(飛ぷ)鳥にどのような思いをもっていたかを挙げてみよう。
イ、速いというイメージ 天鳥船(神代紀下第九段)、山に登ること飛ぶ禽の如く(景行紀四十年七月条)、迅きこと飛鳥の如く(欽明紀五年三月条)、飛ぶ鳥の早く来まさね(『万葉集』971)、高飛ぷ鳥にもがも(同534)の用例がある。
ロ、霊魂の化身またはシンボル 日本武尊の白鳥伝説(景行紀・景行記)に代表される。
ハ、使者・神の使い 天飛ぶ鳥も使ぞ(允恭記歌謡)
ニ、禍 天の血重り飛ぷ鳥の禍(大殿祭の詞)、高つ鳥の災(六月晦大祓)
以上のイメージの中に、直接アスカと結びつくものは考え難い。
網干善教氏⑪は「無限の大空に飛翔する鳥の精悍雄大さ」を宮都アスカに結びつけた。
飛鳥を渡り鳥とみて、渡来人を連想し、渡来人の多いアスカと結びつける説を鳥越憲三郎氏⑫・川田武氏⑬・吉田金彦氏⑭が提唱している。
⑧アスカと(飛ぶ)鳥を類音の言葉を介して結びつける説は多い。
飛ぶ鳥は脚をかがめて飛ぶ。あしかがみ→アスカ。(恵岳『万葉集選要抄』・坐光寺為祥『和歌詞謅』 )
飛ぶ鳥はかすかに見える。かすか→アスカ。(建部綾足『詞草小苑』)
飛び立つ鳥はあわただしい。あわつけき→アスカ。(荒木田久老『万葉考槻乃落葉』)
鳥は朝、ねぐらから出て、まず飛び渡る。朝→アスカ。(富士谷御杖『歌袋』)
鳥は朝明に活動する。朝明(あさけ)→アスカ。(井手至氏⑧)
飛ぶ鳥のアトリ→アスカ。(黒川真頼『古今冠辞考』。折口信夫『万葉辞典』)
これらの類音説は、枕詞「とぶとり(の)」の説明に足りるとしても、宮都の表記にあえて、「飛鳥」を用いた理由を説明するのには、弱すぎると考える。
(三)飛鳥が借訓である場合
飛鳥が「とぶとり」の訓仮名(借訓仮名)として用いられたと考える立場である。
『万葉集』では「山常庭村山有等(大和には群山あれど)」のように、借訓字が多用されている。
従来このカテゴリーの説は少なく、むしろ鳥にとらわれすぎていた感がある。
先の(一)・(二)に満足すべき解答がない以上、鳥から離れて「飛鳥」を考えてみる必要がある。
「とぶとり」とは何か。それはアスカにふさわしい意味を持っていなければならない。
第三章 表記「飛鳥」の背景
アスカと飛鳥の関係を考察するにあたって、飛鳥と表記するに至った動機を推理することは重要である。
まず、表記「飛鳥」が用いられるようになったのは、いつからか。
金石文では、銘文からみれば小野毛人墓誌(677)が最古であるが、墓誌を後に追納する例は多いので、そのまま証拠にならない。
一方藤原宮出土の前記木簡は七世紀末のものとみられる。
網干善教氏は、推古天皇即位から大化改新までに至るアスカの宮名(『日本書紀』による)には「飛鳥」の呼称は用いておらず、大化以後においては、正式の宮名に「飛鳥」を用いるようになつた、すなわち「飛鳥」という名称は大化改新以後であり、飛鳥寺の寺名の変遷も傍証である⑮、とされた。
川副武胤氏は論拠は異なるが、「飛鳥」の表記が天武朝以後と推論している⑩。
一方『日本書紀』・『古事記』・戸籍・官寺の縁起など官撰の文書では「飛鳥」の用例がほとんどであるのに対して、私撰的な『万葉集』では「明日香」が圧倒的に多い。
「飛鳥」はまず朝廷を中心に用いられたと考えてよいのではないか⑯。
大化以後の飛鳥時代は律令国家の形成期であるが、対外関係の活発化に応じて、朝廷は中国・朝鮮の先進文化を積極的に取り入れようとした。
条坊制の都京の構想が練られたり、漢詩漢文も隆盛をきわめてくる。
またたとえば、伝統的な跪礼・匍匐礼を禁止して唐風の立礼に変えたり(天武紀十一)、官人のみならず庶民でさえ、公式の場では唐風の服装をするよう規定している(天武紀十三)。
国際関係における国の体面・体裁を重視した、貴族・官人の国家意識の表れである。
国威発揚を願う「日本」の国号、「天皇」の称号がはっきり用いられるのもこの時代である⑰。
このような背景を考えると、宮都の地アスカの公的表記を唐風に決定することは、焦眉の急務であつたはずである。
唐風の二字の嘉字で、しかもアスカにふさわしい、ことばでなければならない。
これこそ「飛鳥」が用いられた動機であると私は考える。
『続日本紀』和銅六年五月条の命令によって「飛鳥」になったのでなく、アスカが宮都であった故に、他に率先して実行されなければならなかった。
逆に和銅六年の制や、『延喜式』巻第二十二民部上の命令は、この思想の延長であり発展である。
それではなぜ「飛鳥」か。
アスカとすなおに読める二字の好字が得られなかったためか。
あるいは、ヤマトとか倭に関係のない「日本」を国号にしたように、最初からアスカにとらわれず、帝都の地に新しい命名を考えたのかもしれない。
いずれにせよ、アスカを象徴する「とぶとり」と、その表記「飛鳥」が朝廷によって選ばれ決められた、と私は考える。
第四章 「とぶとり」とは何か
飛鳥時代はまた仏教展開の時代、すなわち氏族仏教から国家仏教へと、仏教文化が結実した時期でもある。
宮都アスカは伝統的な宮殿を中心に、エキゾチックな寺院の堂塔がそびえているという、当時としてはきわめて特異な景観を呈していた。
天武紀九年五月条に京内廿四寺の記事がある。その寺名は不詳であるが、飛鳥寺・大官大寺・川原寺・豊浦寺・橘寺・山田寺・奥山久米寺などであろう。
さほど広くないアスカの地に、多数の寺の瓦葺きの大伽藍がいらかを争い、はるか遠くからも望める高い塔が林立していたのである。
当時の人にとって、アスカといえば塔であり寺である。
すなわち、塔と寺がアスカのシンボルであったことに異論はないと思われる。
『日本書紀』での「寺」の初見は欽明紀十三年十月条の浄捨向原家為寺である。漢字「寺」の本義は役所の意味で、後漢の明帝の時代に西域から来た僧が白馬寺を創立してから、寺が現在の意になったとされる。
一方、「てら」は寺の字音ではない。礼拝所を原義とする古代朝鮮語の 뎔( tjəl
)⑱が仏教とともに伝来し、転訛して「てら」に固定したと考えられている。すなわち「てら」は古代朝鮮語由来の外来語であり、借用語である。
インドの初期の仏教では、仏舎利を納めた塔を礼拝した。塔は梵語でstupaといい、古代中国では音訳して「卒塔婆」とか「率都婆」と表し、略して塔婆とも塔ともいう。
『日本書紀』での「塔」の初見は、敏達紀十四年二月条の起塔於大野丘北である。この後、推古四年には飛鳥寺の堂塔が完成している。
日本では現在「とうtoh 」と発音されているが、古くは「 たふtaFu 」であった。「たふ」は塔の字音ではあるが、直接中国からではなく、「てら」と同様古代朝鮮を経由した
外来語の可能性がある。その古代朝鮮語は不明であるが、現代語は 탑( tap )である。
このように、「たふ」・「てら」は朝鮮経由ないし朝鮮由来の借用語とみられるが、日本に塔と寺が伝来した当初、人々はこれらを何と発音したであろうか。
朝鮮からの渡来人や、渡来人と関係の深い人は、そのまま古代朝鮮語で塔・寺を発音したであろう。
しかし一般の人は、この外来語を正確には発音できず、これから転訛した母音終りのことばで、発音したものと考えられる。
外来語が同化されて固定するまでの過渡期には、いろいろの発音が存在する。
近くは、トロッコとトラック、メリケンとアメリカン、ハンケチとハンカチの例がある。
後に「たふ」・「てら」に固定した借用語も、初期には「とぶ」・「とり」と発音された可能性はある。
「たふ」が現在「とう」になったことや、「天飛む(あまだむ)」(記歌謡83・紀歌謡71)も転訛の参考になる。
まして倭語「飛ぶ鳥」の発音との近似性にひかれて、「塔寺」から「とぶとり」を連想し、そのように記憶したり発音することは充分考えられる。
bucket と「馬穴(バケツ)」の関係と同様である。
以上により私は、「とぶとり」とは「塔寺」のことであると主張する。
地名の語源を安易に外国語で解読するむきには批判があるが、朝鮮からの新しい渡来人が多かったアスカとその時代背景を考えれば、私の論は決して牽強付会の説ではなく、逆に従来の諸説より無理がない。
なお、本論とは直接の関係はないが、鞍作鳥(止利)・鳥仏師の「鳥」との暗合には興味が残るところである。
第五章 表記「飛鳥」成立の経緯
結論的に、私は表記「飛鳥」が成立した経緯を以下のように考える。
飛鳥時代の宮廷人は宮都の地アスカの表記として、対外的に恥ずかしくない、唐風の二字の嘉字を求めた。
アスカと直接読める適切なものが得られなかつたためか、あるいは初めから新しい命名を考えたためか、アスカを象徴する塔寺に由来する「飛鳥」を採用した。
そのまま「塔寺」では、国際的にも不適当だからである。
塔寺を「飛鳥」にしたのは、
①すでに以前から、塔寺と「飛ぶ鳥」が類音のために連結され(馬穴の例)、一般的であったのをそのまま採用したものか、
あるいは②「飛鳥」の字に塔寺だけでなく、鳥の意味も重層的に含ませる意図によったのか。
①・②のいずれか、または両者のためと考えられる。
『万葉集』には装飾的・技巧的・重層的に文字を使用した例は多く⑲、「蚊蛾欲布虚蝉之妹蛾(かがよふうつせみのいもが)」(万2642)と意識的に虫に関する文字を使用したり、「有猿尾(あらましを)」・「相見鶴鴨(あひみつるかも)」のような用例がある。
「飛鳥」にしても、原義はあくまでも塔寺であるが、副次的に鳥の意味をも重層させた可能性は否定できない。
この場合は、第二章(二)の諸説が生きてくるわけである。
終わりに、.枕詞「飛鳥」との関係に触れておきたい。
アスカを「飛鳥」と表記するのは、アスカにかかる枕詞「飛ぷ鳥(の)」に由来するとの説は古くからあり、現在も根強く残っている。
しかし、これは根拠のない断定であり、枕詞が地名表記「飛鳥」の使用以前から存在していた証左は、まったくない。
さらに『万葉集』で「飛鳥」が、アスカまたは浄之宮にかかった枕詞としての用例は、意外に少なく五首のみである。
そのうち三首は柿本人麻呂の作であり、689年没の草壁皇子への挽歌(万167)、691年没の川島皇子への挽歌(万194)、700年没の明日香皇女への挽歌(万196)である。
他の一首(万78)は平城京遷都時(710)の元明天皇御製とも、藤原京遷都時(694)の持統天皇御製ともされる。
残る一首(万3791)のみは、作歌年代が不明で竹取翁の作とされている。
以上の事実と人麻呂の作風からみて、枕詞「飛鳥」が人麻呂の創作でないかとする、吉永登氏の説⑳がある。
地名表記「飛鳥」と枕詞「飛鳥」の関係を考察することは本旨ではないが、いずれが先かによって、次の二つの場合が考えられる。
①枕詞が先に存在した場合。「塔寺(の)」は、土地ほめの働きがあり、アスカの冠辞としてふさわしいものである。
ただし、塔寺から転訛した「とぶとり」が口誦性のもので、「飛鳥」の字がまだ使用されていなかった可能性も、保留しておかねばならない。
地名表記はこの枕詞をヒントにして、「飛鳥」と決定されたとみるのである。
②逆に、地名表記から枕詞が生まれた場合。
本章のはじめに述べた経緯で、表記「飛鳥」が決められたのち、これからアスカにかかる枕詞がつくられたことになる。
現在の史料では①・②のどちらとは決められないと考える。
なお枕詞の問題はさておき、宮廷歌人の地位と特異な作風(21)を考えると、人麻呂がアスカの表記の公式決定の場で、あるいは重要な役割を果たしたのかも知れない。
〔注〕
①岸俊男「飛鳥と方格地割」『史林』53-4
②奈良国立文化財研究所飛鳥資料館編『日本古代の墓誌』昭54
③奈良国立文化財研究所飛鳥資料館編『飛鳥・白鳳の在銘金銅仏』昭54
④岡崎敬『古代の日本9』昭46、角川書店
⑤奈良国立文化財研究所『藤原宮木簡一』昭53
⑥奈良国立文化財研究所『木簡検索データべース』
⑦福井久蔵『枕詞の研究と釈義』新訂増補、昭35有精堂出版
⑧井手至「飛鳥考」『万葉』79号、昭47
⑨土橋寛「古代歌謡と飛鳥」『明日香村史』中巻、昭49、明日香村史刊行会
⑩川副武胤「飛鳥考」『史学雑誌』89-4
⑪網干善教『飛鳥の遺蹟』昭53、駿々堂出版
⑫鳥越憲三郎『飛鳥へのふるみち』昭48、新人物往来社
⑬川田武『二つの飛鳥』昭48、新人物往来社
⑭吉田金彦『古代日本語をあるく』昭58、弘文堂
⑮網干善教「飛鳥の宮跡」『飛鳥を考えるⅢ』昭53、創元社
⑯門脇禎二『新版飛鳥』昭52、日本放送出版協会
⑰上田正昭「飛鳥文化とその背景」『飛鳥再考』昭54、朝日新聞社
⑱金思燁『古代朝鮮語と日本語』昭49、講談社
⑲川端善明「万葉仮名の成立と展相」『文字』昭50、社会思想社
⑳吉永登「トブトリノ明日香」『橿原考古学研究所論集創立三十五周年記念』昭50、吉川弘文館
(21)梅原猛「聖徳太子と人麿」『飛鳥再考』昭54、朝日新聞社